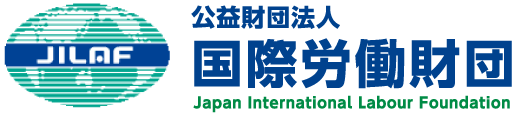2024年 スリランカの労働事情(アジアユース英語圏チーム)
以下の情報は招へいプログラム「アジアユース英語圏チーム」参加者から提出された資料をもとに作成したものである。
参加者情報
セイロン労働者会議(CWC)
スリランカ・ニダハス・セワカ・サンガマヤ(SLNSS)
1.最近の労使紛争についての取り組み
(1)CWCの事例
<農園労働者の賃金引き上げをめぐって>
①経過
茶栽培・製茶ならびにゴム栽培・生産に携わる農園労働者の賃金を巡る紛争の事例。スリランカでは労働組合は企業別ではなく、産業横断的に組織されているが、農園労働者を組織するセイロン労働者会議(CWC)、ランカ・ジャティカ農園労組(LJEWU)、合同農園労組センター(JPTUC)は、地域の22の農園企業を代表する使用者団体との間で1967年に労働協約を締結し、依頼、定期的に労働協約の改定を行ってきた。
2021年の労働協約改定に際し、労働側は使用者側と賃上げ交渉を行ったものの、使用者側の理解を得ることができず、交渉は不調に終わった。これに対し、労働側は政府の賃金委員会に訴え出て、結果的に1日当たり基本給を900ルピーとすると共に、「家計救済手当」(「労働者の家計救済手当に関する法律」に基づく手当)を100ルピーとする、計1000ルピーの日給を獲得した。しかし、このことにより、以降使用者側は労働協約改定の協議には応じなくなった。
2024年、COVID-19の影響と2021~22年のインフレとにより生計費が3倍になっている状況にあることを背景に、労働側は、政府の賃金委員会において、1日当たり基本給を1700ルピーに引き上げることを求める裁定を申請した。これに対し使用者側は、経営を維持することが困難になるとしてこれを拒否し、控訴裁判所、更には最高裁にまで訴え、労働側はその対応を余儀なくされた。
②結果
2024年9月10日、CWCを筆頭とする労働団体は、1日当たり基本給を1350ルピーとし、生産出来高に応じたキロ当たり付加給を50ルピーとすることで、妥協した。
なお、CWCは1日当たり基本給を1700ルピーに引き上げることを諦めた訳では無く、今後とも引き上げに向けた活動を継続していくことにしている。
(2)SLNSSの事例
1)COVID-19の影響を受けた航空会社での紛争
①経過
スリランカ航空はCOVID-19の影響を受け、深刻な危機に直面した。即ち、2020年4月から全便の運航を停止すると共に、いくつかの路線を廃止せざるを得ない状況に陥った。そして、それでは収まらず、400人の契約社員の解雇、正社員の賃金カットが決定された。
②SLNSSの対応と結果
SLNSSは、スリランカ航空支部組合員のこうした困難な状況に対し、スリランカ航空経営陣ならびに政府との話し合いを続けた。継続的な話し合いと粘り強く行われた要請の下で、解雇された者の苦境が明らかにされ、などが判明し、実態についての経営側の理解が徐々に進んでいった。
その結果、COVID-19が終息した際には職を失った全従業員の復職を約束するとの文書を労使で取り交わすことができた。そして、契約社員全員が固定給で再雇用されるに至った。
2)バス運行労働者のボーナス支払いをめぐる争議
①経過
西部州道路旅客輸送局の管轄下でバスの運行に携わっている従業員に対して毎年4月に支払われてきたボーナスが、正当な理由も示されないままに2016年は支給されなかったことをめぐる紛争である。
SLNSSは2016年のボーナスの支払いを求めて、旅客輸送局のトップをはじめとする経営陣との交渉を続けたが、ポジティブな回答は得られずじまいであった。そこで、労働側は、全ての従業員の支持を背景にしてストライキに踏み切った。
②結果
ストライキにより全ての本部業務がストップし、地域事務所も全て閉鎖された。ストを背景にして交渉を続けた結果、2016年のボーナスとして2万ルピーを支払うとの案で経営側と合意し、7日間続いたストライキを終結させることができた。
2.労働法制・社会保障法制の現状と課題
(1)現状
労働関連の法律は数多くあるが、その一部を例示すると次のとおり。なお、主要法規のいくつかは英国植民地時代に英国によって制定されたものだが、必要な改正を経ながら現在も適用されている。
- 店舗及び事務所従業員の雇用及び報酬に関する法律
- 工場法
- 女性、若年者、児童の雇用に関する法律
- 出産手当法
- 労働者災害補償法
- 労働者の雇用の終了に関する法律
- 賃金委員会法
- 最低賃金法
- 労働者の家計救済手当に関する法律
- 労働争議法
- 労働組合法
- 被雇用者準備基金法
- 被雇用者信託基金法
(2)課題
①労働法改定問題
2024年9月の大統領選挙、11月の議会選挙を経て新政権が発足。
前政権は国の経済危機に際しIMFからの支援を求めざるを得なかったが、IMFはその支援の条件として「主要な労働法を大幅に緩和し、使用者にとって使い勝手の良いものにする」ことを求めてきた。前政権は、多くの労働組合の反対にも拘らず、労働法の規制を緩和する法案を新政権発足前に国会に提出していたが、可決にた至っていない。新政権がこの法案に対してどのように対処するのか注目しているところである。
②年金制度
公的年金の受給権が保証されているのは公務員と銀行職員のみである。なお、公務員年金の場合は、財源は国庫負担となっており、本人拠出は発生しない。
他方、民間で働く正規部門の労働者には、「被雇用者準備基金(EPF)」への加入が義務づけられている。EPFの財源は労使の拠出金で、労働者は毎月賃金総額の8~10%を、使用者は12~15%を支払うことになっており、基金の管理は政府が行っている。積み立てられた基金は労働者の退職時に一括払いの形で支払われるが、この仕組みは労働者にとって十分なものとは言えず、一定額の一時金と終身払いの年金の組み合わせが理想的である。従って、そのような年金制度への転換の提案に向けて、現在、検討を行っている。