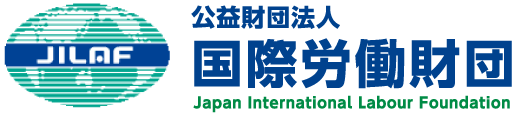2024年 インドの労働事情(アジアユース英語圏チーム)
以下の情報は招へいプログラム「アジアユース英語圏チーム」参加者から提出された資料をもとに作成したものである。
参加者情報
インド全国労働組合会議(INTUC)
インド労働組合(BMS)
インド労働者連盟(HMS)
1.最近の労使紛争についての取り組み
(1)INTUCの事例
①経過
グローバルに事業展開しているインドの企業(バイオエネルギー・製薬業関係企業)で紛争が起きている。労働組合が有期契約労働者(10年以上同企業に従事)を正社員として雇用するよう会社側に要求したところ、使用者は団体交渉を拒否し更に一部ぎょうむを外注するようになった。
②結果
現在もこの事案は法廷で争われているが、使用者側は有期契約の労働者に依存していく姿勢にある。なお、当該労働者は、既存の契約条件で現在も雇用されている。
(2)BMSの事例
①経過
ある大規模繊維業で起きた労使紛争でストライキに至った最近の事例である。事の発端は、労働組合がインフレ率をカバーする賃上げとして20%アップを要求、併せて、安全規定の改善と義務的残業時間への上限設定を要求したことにある。使用者側は、これに対し、財政事情と市況を理由に、受け入れることは出来ないと回答した。但し、より低い賃上げ率であれば受け入れる余地があるとし、安全への配慮についても約束したが、交渉は長引き、労働組合は2週間にわたるストライキを決行した。
②結果
争議にBMSが介入するに至り、企業の財政事情を考慮すれば大きな前進と言える10%の賃上げ回答を得ることができ、市況を勘案しつつ6ヶ月後に賃金問題を再度検討することが約束された。加えて、安全規定を強化することが約束され、それには定期的な安全監査の実施、安全に関する従業員教育の強化、より安全な保護具の提供が含まれた。さらには、義務的残業時間の上限についての合意にも至り、労使の対話を促進すべく労使合同委員会を設置することも確認された。
この争議は、組織化された労働者の交渉が実質的な結果をもたらすことができることを実証し、また労使が建設的な関係を結ぶことで更なる紛争を防止することについても確認される機会となり、当該企業は地域や他のステークホルダーから責任ある経営者としてポジティブに受け入れられることとなった。
(3)HMSの事例
①経過
紹介する労働争議は、鉄道の乗務員用ロビーの拠点を他の大都市に移転することを巡って起きたものである。乗務員用ロビーとは鉄道乗務員の乗車登録、指示書配布、降車登録などが行われる地元の管理センターであるが、鉄道職員は一般的にロビーに近接する官舎で家族と共に生活している。ロビーの他の大都市への移転は、生活費の高騰だけではなく、教育・医療・福祉・地域サービスなどの面での付随する様々な問題を生じさせることになり、労働者に大きな困難とストレスを与える変更である。
従って、労働組合は、移転先の都市にも乗務員用の官舎ならびに付随する地域サービスが確保される必要があるとの立場から、そのことを、乗務員の移転先への移動の条件として要求した。
②結果
労働組合は使用者側である鉄道局との様々なレベルでの交渉に臨んだものの、使用者側は頑なに要求を拒み続け、労働組合は、デモ、ハンストなどの争議行為を行うほか、マスメディアへの働きかけを行った。その結果、高名な労働組合指導者が介入するに至り、問題は解決に向かった。最終的に、乗務員用ロビーの移転計画は撤回されるに至った。
2.労働法制・社会保障法制の現状と課題
(1)現状:法改正により4つの法典に再編
政府は、経営側による法律遵守を容易にすると共に、時代に即した内容とし投資促進にも寄与するものにするとの考え方を背景として、複雑な法体系の簡素化に取り組んだ。その結果、29の個別法を4つの法典に再編した法案が2019年から2020年にかけて連邦議会で可決された。制定された4つの法律は以下のとおり。
- 2019年賃金法
- 2020年社会保障法
- 2020年労働安全衛生・労働条件法
- 2020年労使関係法
なお、労働法は国と州との共同管轄となっているため、各州が連邦法の改正に則した施行規則を規定しない限り法が施行されないこととなっている。現在、一部の州のみが施行規則を規定したにとどまっており、従って、改正法の主要な条項のほとんどが未施行の状態のままである。
(2)4法についての受け止めと課題
①全体的な受け止め
労働組合は、4法にはポジティブな面とネガティブな面の両面があると受け止めている。即ち、労働法を簡素化・近代化するとの目的には賛同できる一方で、法制定過程にすべての労組ナショナルセンターの関与を保証することもなく、意味ある協議が行われたとも言えず、一方的な進め方がなされた結果、労働者の権利の保護に大きな懸念が残るものとなり、非常に残念である。また、法は制定されたものの、法の施行に向けた諸制度の整備には技術的課題が山積している。
②労働者の権利の保護への懸念
-
- ストライキ実施のハードルが上がった。即ち、ストは、開始前14日から60日までの間に使用者に対して通知しなければならず、事前通知のないストは違法ストとなる。
- 解雇・人員削減・事業所閉鎖に関する規制が緩和された。即ち、解雇・人員削減・事業所閉鎖をする場合に使用者は州政府から事前許可を得る必要があるが、その適用対象となる事業所における労働者の人数要件が100名から300人へと引き上げられ、大幅に緩和された。
- 就業規則の作成に関する規制が緩和された。即ち、就業規則の作成が義務づけられる事業所が、100人以上を雇用する事業所から300人以上を雇用する事業所へと規模が引き上げられ、大幅に緩和された。
③適用範囲の問題
-
- 出産や子育てに対する支援が適用される対象が限定的なものとなっている。
- インフォーマルセクターの労働者が法の適用対象外になっている。但し、今回の改正で、社会保障法においては、ギグワーカー、プラットフォームワーカーなどもその適用対象とすることとなった。
④今後に向けた課題
-
- インフォーマルセクターの労働者がより一層、法で保護されるようにすることが重要である。と同時に、彼らが自分たちの権利や法に基づく保護について知ることのないままに放置されていることから、その周知に向けた取り組みと、実際に法が執行されるようにすることが重要な課題になっている。
- 今回の法制定過程において労働組合の参加が軽視されたことは重大な瑕疵であり、労働側も参加する実効性ある社会対話の確立が欠かせない。